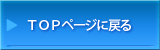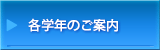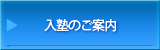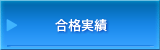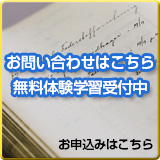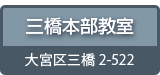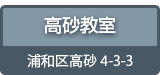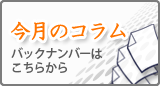今月のコラム 文⁄塾長 大山重憲
到来
父は優しい人だった。私が小学生の時、インフルエンザで寝込んでいた時に忙しい仕事の合間を縫ってイチゴを買って持ってきてくれたことが、父の優しさを感じた最初の思い出である。
母が脳腫瘍に倒れて施設に入所してからは、最期の日まで一日たりとも欠かすことなく食事の介助に通い、母の好きなものをよくわかっていて、水ようかんやお団子を持って行っては「美味しいだろ」と笑顔で声掛けをしながら辛抱強く食べさせていた。そばで見ていて、頭が下がった。
何でも作ってしまう職人顔負けの器用な人、創意工夫する人だった。既成の物では満足せず、何かしら手を加えて自分のオリジナルな作品を作ってしまう人だった。実家の新築の時も自らスジカイを入れて「地震が来てもこれならびくともしない」と自慢していた。
お酒の好きな人だった。アル中にならなかったのは創業した自分の会社があったからである。仕事に向かう父の真剣な背中を見て、私も弟も育った。
釣りが大好きだった。ゴルフ、詩吟は「そのくらいの付き合いがないとダメ。教養がないとダメ」と、亡き母に勧められてのことだった。ONロータリークラブの発足メンバーでもあり、忙しい中を週一回の例会に出席し、会長を務めた一年間は、例会直前にスピーチの原稿を辞書をくくりながら大慌てで書いていた姿を思い出す。
あまり私や弟と正面から向き合うことをする人ではなかった。が、私たちに対する期待が大きいことはいつも感じてはいた。私も弟も父にはずいぶん苦労をかけた。今、後悔があるとしたら、もっと腹を割って本音で語り合いたかったこと、そして、父が母にしてあげていたようには、私たちは父にはしてあげられなかったことである。父だったら、自分自身に、どうしてあげただろうと思うと、申し訳なさでいっぱいである。父のその優しさを、これからは手本にして生きていきたいと思う。
人が普通しない苦労をした人でもあった。父が茨城に出張で留守の間に火災に遭った時、帰ってきた時の父の茫然とした表情は、今でも脳裏に焼き付いている。
晩年は病気がちだった。胆嚢摘出、胆管結石、脳梗塞、そして昨年の心臓の三本のバイパス手術と大動脈弁の手術は14時間に及んだ。今年5月の肺がんの放射線治療を行ってからは、特に弱っていった。今年の夏は異常な暑さで、8月半ばの予定の通院日前日に見た父は、骨と皮ばかりの状態だった。主治医に「このままでは死んじゃうから、入院せてもらいたい」との父の真剣な訴えは、最後の叫びになった。
それから一週間の入院後、配食サービスの介護食を摂り始めたが「匂いが鼻についていやだ」と言って2週間ほどで食べなくなり「何か食べたいものは?」と聞くと「おにぎりが食べたい、アンパンが食べたい」と。しかし、買ってきても目の前にすると「食べられない」という日が続き、9月に入ってからは日を追うごとに弱っていった。そして、「おなかはすいているんだけど、食べられないんだよなあ」と言う日が続き、最期の日を迎えたのだった。
父の遺影は、8月19日、父の満84歳の誕生日の前日、実家でわざわざお気に入りの服と帽子をまとって、私の次女が撮ったスナップ写真で「これを遺影に使ってほしいと」遺言していたものである。父の最後の笑顔が優しさをにじませているように感じる。
天寿を全うし、生命の炎を燃え尽くしたのではないかと思う。今頃は天国で亡き母や父の両親兄弟と久々の再会を果たし、麗しい時間を笑顔で過ごしているのではないかと思う。
いよいよ「時が来た」と感じる。「前を向かないと」と思わせられている。