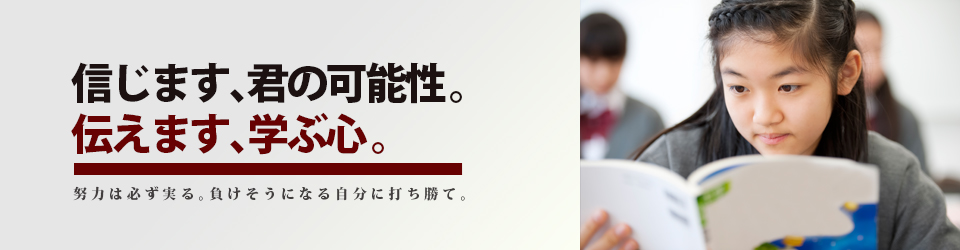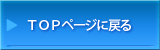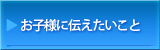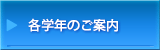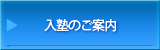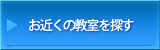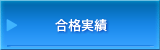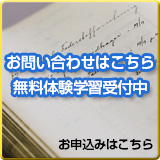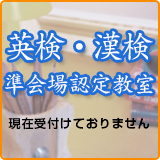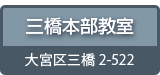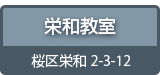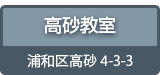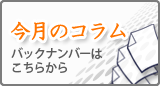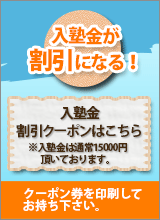今月のコラム 文⁄塾長 大山重憲
放し亀
江戸の頃、栄えた両国の橋詰に「放し亀」というのがあった。たいてい、おじいさんが売っていたという。春と秋のお彼岸にお墓参りの方がその亀を買って隅田川(=大川)に流す。これが生き物の命を助けたということで仏様に供養になったというところから「放し亀」は大変に繁盛したという。
落語の小噺にこういうのがある。
「いらっしゃいまし。」
「おやじさん、この大きい亀はいくら?」
「お目が高うございますね。皆さん大きいのにすぐ目を付けまして。こちらは16文でございます。」
「ほー。そば一杯の値か。いい値だね。こっちにいるこの小さいのはいくら?」
「それでございましたらお客様、8文でございます。」
「半値だ。よし、その8文のを買った。じゃあ、ここへ置いたよ。この亀貰っていくからね。亀よ、二度と捕まって不自由な真似をするんじゃねえぞ、いいか。大川へ放してやるからな、自由になれよ。」
ポーンと放してやって「ああ、いいことしてやった」というのだが、これは「善に似て善に非ず」と言う。何故かというと、確かに8文で助けてもらった亀は自由になっていい。しかし、最初に聞かれた16文の亀の気持ちになってごらんなさい。たまったもんじゃない。「助かったなー」と思ったらワーッと向こうへ行っちゃった。歓喜から絶望へ。「善人があるので亀が酷くされ」と言われる。何が善で何が悪であるかというのはなかなか難しい。どうせ助けるのなら平等に助けなけりゃいけないと、そこらを言っているのだろう。
大宮公園に車で行く途中、交差点で信号待ちをしていて、ふと左に動く物が視界に入ってきた。何だろうと見たら、亀だった。しっかりした足取りで一軒家のコンクリートのガレージを歩いている。と、その家の車の下に入って行ってしまった。瞬間、思った。「放って置いたら車道に出てきて車に牽かれてしまう。」すかさず車を左に寄せて停めてその家のインターホンを押した。
幸運にも応答があった。
「Kさんですか?もしや、亀を飼っていませんか?」
「はあ?」
怪訝な反応である。無理もない。全くの他人に呼び鈴押されて亀を飼ってないかと聞かれたら誰だって何の話?となるのは普通である。
「少しいいですか?」
中から現れた人は90歳は越えているだろうおばあさんだった。
「亀を飼っていませんか?」
「いいえ。」この人何言ってんの?という表情だ。
「亀が元気に歩いてお宅の車の下に入って行ってしまったんです。このままにしておいたら車道に出て行って車に牽かれて死んでしまうかもしれないと思って。車の下を見させて頂いてもいいですか?」
「あら!」
おばあさんも「えらいことだ」と思ったのだろう。「どうぞどうぞ」と許可してくれたので両膝を突いて覗き込んでみた。いない!確かに車の下に入って行ったのに。と、車の周りを見回したら、いたいた。細く小さな花壇の草の上にちゃっかり五体を引っ込めた状態で、いたのだ。体長15